- 6月29日、新たな組合が誕生しました
- 結成の経緯
- 組合が新人事制度導入延期を勝ち取る
- 恵佑会ユニオンKICK-OFF MEETING開催
- 組合が配ったチラシが回収される!?早速の不当労働行為か…
- 第1回団体交渉開催
- 法人「新人事制度で低賃金層の底上げ!若手職員の処遇改善!」→組合「やってること矛盾してませんか…?」
- 組合「新人事制度導入は理事会が決めたの?」→法人「いいえ。窓口は事務部長です」
- 組合「新制度で事務部長の基本給の上限が15万上がるけど、それこそ低賃金層に分配すべきじゃない?」→法人「…。」
- 法人「新制度で基本給アップ!退職金も増えますよ!」→組合「え…じゃあ、なんで基本給の上限をさげるの…?」→法人「…。」
- 次々に浮き彫りになる矛盾…。結局新制度導入の目的はなに?
- 組合「新制度では看護師の基本給の上限が約7万円下がりますが、そうなると退職金も下がりますよね?」→法人「そうです…。」
- 組合「評価者はちゃんと評価できるの?どうやって訓練するの?」→法人「コンサルにトレーニングしてもらいます…」→組合「??」
- 不当労働行為発生??
- 第1回団体交渉を終えて。感想など
6月29日、新たな組合が誕生しました

北海道屈指のがん治療専門病院として知られている、恵佑会札幌病院で労働組合が結成されました。
今回、法人の不透明な新人事制度の導入と各種手当の廃止、および減額案に疑問を持った放射線技師や薬剤師、看護師たちが声を上げ、6月29日、法人に対し、誠実な説明と協議を求め、団体交渉の申入れを行いました。
結成の経緯
法人は、7月1日から新人事制度の導入を計画していました。
その新人事制度は、基本給の見直し、評価制度の導入、各種手当の減額および廃止が盛り込まれたもので、職員にとっては非常に大きな不利益変更も含むものでした。
しかしながら、そのことが告知されたのは、制度導入の2週間前を切った6月19日でした。
その後、導入予定日の5日前に説明会が行われましたが、一方的なものと言わざるを得ず、職員たちは困惑しました。
あまりに急な通告、そして、十分とは言えない説明…。法人が意図してそうしたとは言えませんが、労使間の理解に大きな溝を作りました。
このままではまずい…
職員たちは、「賃金の減額という生活に直結することについて、十分な説明もないまま導入される」ことに疑問を覚えました。
実際、このようなプロセスで不透明な人事制度が導入されれば、法人と職員の信頼関係は崩れ、気持ちよく仕事ができる環境が作れなくなることは必至です。そのような事態は避けなければなりません。
明らかに労使コミュニケーションが不足している状態を是正するため、そして、今後も気持ちよく働く環境を守るためには、労働組合を結成し、労使対等で、互いに誠実に、建設的な協議をすることが一番望ましいと考え、組合結成に至りました。
手当が大幅に削減され、年収50万円下がるケースも
法人側の説明では、新人時制度導入によって、「環境の変化へ柔軟に対応し、従来の枠組みにとらわれることなく変えるべきものは変えるスタンスで変更していきます。(中略)今後の職員一人ひとりの業務ややりがいや成長に寄与していく」とのことです。
しかし、直前に行われた説明会においては、詳しく知らされない部分が多くあり、実際どのように運用されるのかは分かりません。
賃金改定によって手当が上がる人もいますが、年収にしておよそ50万円下がるケースも想定されます。さらに基本給の上限が下がることによって、退職金が大幅に減額される恐れもありました。
また、薬剤師の資格手当がゼロになり、寒冷地手当も大幅に削減され、持ち家に対して住宅手当が支払われなくなります。
昇給と夏季ボーナスも毎年の人事評価によって左右され、昇給幅とボーナスの支給額が管理職による評価に委ねられてしまうことになります。
組合との協議を経ない労働条件・就業規則の変更は無効

6月29日の申入れでは、今回の新人事制度について組合と誠実に協議をすることを要求しました。
団体交渉の議題に上がったことを組合と協議なしに変更をすることは、労働組合法第7条の不当労働行為に抵触する違法行為となります。
並びに、労働者側との合意を経ない就業規則の不利益変更は、労働契約法第9条に違反し無効です。
組合の申入れによって、新人事制度の導入は一時ストップされました。
労働契約法第9条
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
組合が新人事制度導入延期を勝ち取る
6月29日の組合からの申入れを受け、法人は組合に対し、「今般のお申し入れを受けまして、新人事制度(賃金制度)の導入は一旦保留とすることを正式に決定」する旨の通知をしました。
組合の申入れがきっかけとなり、制度の導入を一旦は止めることが出来ましたが、法人は「新人事制度の導入および制度の大枠については変更なく進めていく」としており、あくまで延期ということで、今後も導入を進める姿勢です。
恵佑会ユニオンKICK-OFF MEETING開催

小野寺信勝弁護士(写真右側手前)
7月16日、恵佑会ユニオンは、団体交渉に向けてのキックオフミーティングを開催しました。
集会には多数の組合員が参加し、さらに今後恵佑会ユニオンを強力にサポートする北海道合同法律事務所の小野寺信勝弁護士に、今回の新人事制度導入の手続きは労働法の要件を満たさず無効であること、および新人事制度の中身についても、合理性がなく無効であることを解説してもらいました。
小野寺信勝弁護士のプロフィールはこちら
組合が配ったチラシが回収される!?早速の不当労働行為か…
組合を新しく結成したため、組合員を増やすためにチラシを配布しています。
恵佑会病院はシフト交代制で、就業時間が職員によって異なるため、多くの職員にチラシを配布するために、組合員が休憩時間に各部署を回っています。
当然、就業時間中の職員を引き留める訳ではなく、就業の邪魔にならない範囲でチラシを渡して帰るか、誰もいなければ机に置くのみです。
しかしながら、法人は組合員の上司を呼び出してチラシ配布について注意し、ある部署では配布されたチラシを回収しているようです。チラシ配布は憲法28条団結権などで保障された組合の権利です。
日本国憲法 第28条 【勤労者の団結権】
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
我々は、組合員であると同時に医療現場の最前線で働く医療従事者です。誰よりも現場を知っています。つまり、それを踏まえて、仕事の邪魔にならないように最大限の配慮をしたうえで、チラシ配りをしています。
また、法人が主張している「就業の邪魔になっている」との報告があったという話も具体的にどのような邪魔になっているかの説明もありませんし、その上、その事実があったとされる時間や場所も、組合が把握しているものと合致しません。
団体交渉で、このことを法人に伝えたのですが、法人から有効な回答も反論もありませんでした。
なぜこのような主張を法人がするのか意図はわかりませんが、組合が就業の邪魔をすることはあり得ません。法人の主張はとても残念です。
第1回団体交渉開催

7月31日、白石東町づくりセンターにて団体交渉を開催しました。
法人からは、恵佑会札幌病院院長、事務部長2名、法人側代理人としてS法律事務所からY弁護士ら4名が出席しました。
法人「新人事制度で低賃金層の底上げ!若手職員の処遇改善!」→組合「やってること矛盾してませんか…?」
法人は、新人事制度導入の目的について、「低賃金層の底上げをしたい」「若手職員の処遇を改善させたい」と主張しました。
しかしながら、新制度の内容を紐解いていくと、法人が目的としている主旨と全く真逆の状態になります。
法人は、低賃金層の底上げをするためと言いながらも、実際は手当が減額・廃止されたり、評価制度によって昇給が抑制されることで、低賃金層の職員は、より一層年収が下がる恐れがあります。
特にコメディカル職員の若年層は、賃金が下がる事は必至です。
また、新人事制度では、基本給の上限が下げられるため、早ければ40代半ばで昇給が止まります。
これでは、若手が頑張って、長く働き続けようというモチベーションを保てません。
さらに法人は、新人事制度導入の理由のひとつとして「現行の給与体系が時代にそぐわないため」とも言っています。
何を根拠にこのようなことを言っているのか抽象的すぎて納得できませんし、制度の内容についてもきちんと答えてもらえてないことも多く、今後より深い労使コミュニケーションが必要だと感じました。
組合「新人事制度導入は理事会が決めたの?」→法人「いいえ。窓口は事務部長です」
団体交渉で、新人事制度導入の経緯を法人に質問しました。
これだけ重要な制度導入に際して、誰がどのように決めたのかは、とても気になるところです。
組合が、理事会で新人事制度について、どのように話し合われたのかを聞いたところ、法人は「理事会本体で打合せはしておりません。理事会と構成員が同じ幹部会議と言うのがあるんですけど、その中で話し合いをさせて頂いて進めた。」と回答しました。
組合は、いくら理事会と構成員が一緒であっても、このような重要なことを最高決定機関である理事会を通していないことに不信感を抱きました。
そこで、組合は質問を変えて「今回の新人事制度を提案したコンサルティング会社を決めたのは誰なのか?」と質問をしました。
ちなみに新人事制度は、とあるコンサルティング会社が作ったもので、法人が独自に職場のこと、および職員のこと、患者のことを一から考えて作ったものではありません。
法人は「理事長と事務部長が協議して決めた」と回答しました。さらに、窓口になって主導的にコンサルティング会社を選定したのは事務部長であったことが団体交渉でわかりました。
つまり、話を整理すると事務部長がコンサルティング会社の新人事制度の提案を受け、他の候補もあったが、今回のコンサルティング会社を選び、理事長に提案し、決定したということになります。
どのような目的をもって、事務部長がこのコンサルティング会社を選定したのかはわかりませんが、全体の印象として、残念ながら納得できる話ではありません。
組合「新制度で事務部長の基本給の上限が15万上がるけど、それこそ低賃金層に分配すべきじゃない?」→法人「…。」
また、団体交渉で法人は、「全体の人件費の総枠は変えずに配分を変えて低賃金層の底上げをしたい」と主張しました。
法人の言っていることは素晴らしいですが、そうであれば、役職者などの高所得者から若年層へ再配分するなどの対応が適切ではないでしょうか。
しかしながら、新人事制度では、役職者は全体的に賃金が上がります。特に事務部長は基本給の上限が15万円ほど増額になります。
組合は、団体交渉でこの事実について主張しましたが、法人からは有効な回答、および反論はありませんでした。
確かに、法人が新制度導入に際して説明した「職位者に対してマネジメント負荷に見合う処遇を実現する」という目的は理解できます。しかしながら、そこだけに着目して現場が上手く回っていくでしょうか。それが病院の利益、および患者の利益、職員の利益につながるでしょうか。
役職者の賃金を上げて、病院の中核を担う看護師やその他のコメディカル職員の賃金を下げる。そんな単純な話でうまくいくとは考えにくいです。
法人「新制度で基本給アップ!退職金も増えますよ!」→組合「え…じゃあ、なんで基本給の上限をさげるの…?」→法人「…。」
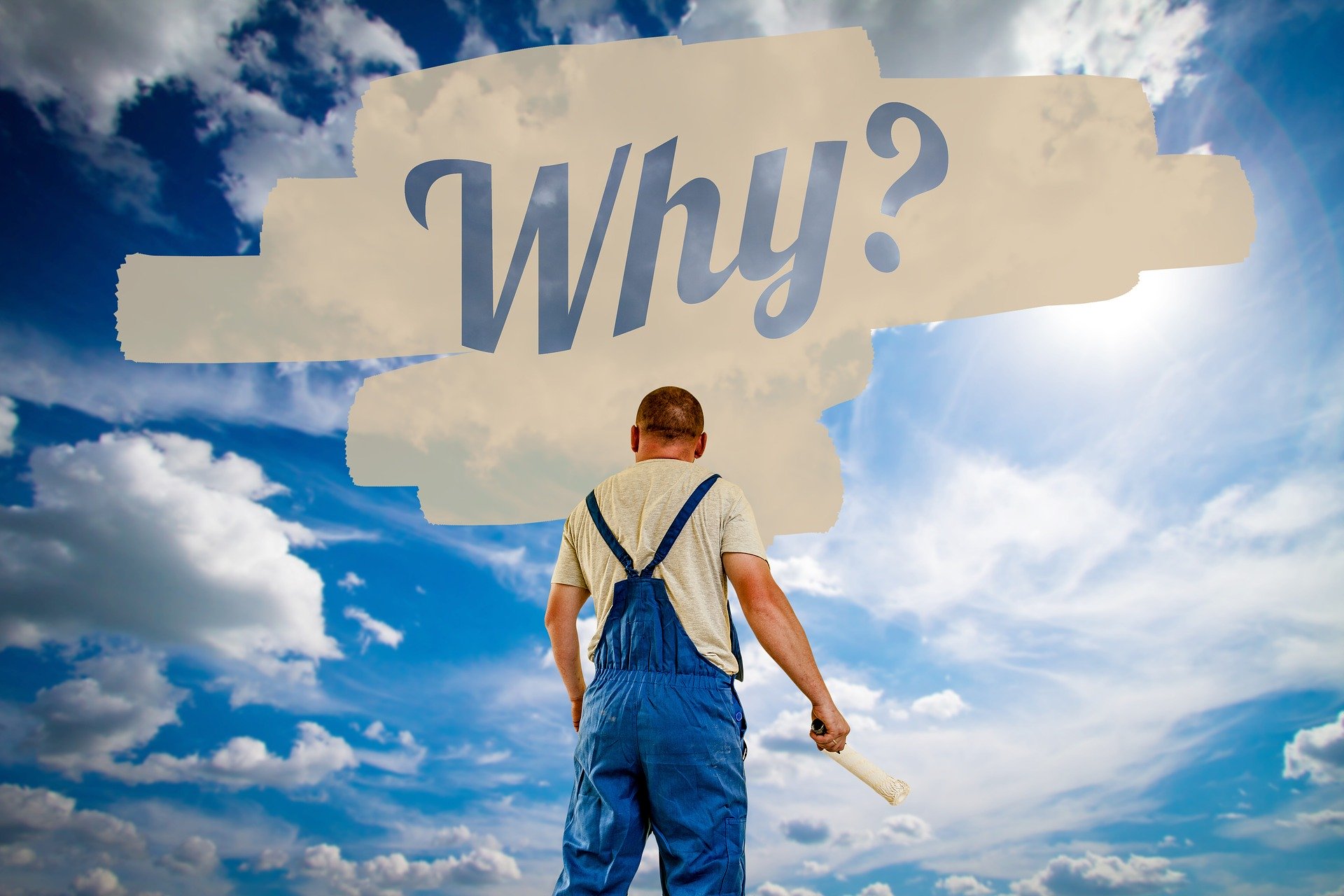
法人は、新制度で減額、あるいは廃止される手当を基本給に組み込んでいく方針で、基本給を上げることによって、退職金が増えると強調しました。
組合は、「では、何故基本給の上限を下げるのですか?」「そのような主旨の制度なのであれば、手当をすべて基本給に組み入れればよいのでは?」と質問をしました。
しかし、法人は明確な回答をしませんでした。また、説明会では減額した手当は基本給に組み込むことを説明したつもりと述べました。
一部の職種の一部の手当を基本給に組み込むことは、説明資料に明記されていましたが、それ以外の減額または廃止された手当が基本給に組み込まれることは聞いていませんし、もし説明があったとしても、大多数の職員は、理解していないと思います。
次々に浮き彫りになる矛盾…。結局新制度導入の目的はなに?
組合の質問に対し、具体的な説明も反論もない法人の対応…。
また、法人は、『「新人事制度」の導入は決定事項であるが、その導入にあたって組合と協議することは必要な手続きである。』と述べていますが、そもそも新人事制度導入の必要性が検証されていません。
法人が主張するように、人件費の抑制が目的ではないというのであれば、新人事制度の導入により所得の下がる職員が1名たりとも出てはならないのではないでしょうか。
新制度導入の本当の目的は一体何なんでしょう。「実際は勤続年数の長い職員のコストカットなのでは?」と考えざるを得ません。
組合「新制度では看護師の基本給の上限が約7万円下がりますが、そうなると退職金も下がりますよね?」→法人「そうです…。」
看護師の基本給上限引き下げ問題について質問をしました。
組合は「新制度が導入されれば、看護師の基本給の上限が7万円下がる。そうなれば退職金が下がる。特に役職のついていない定年間際のベテラン看護師の退職金が下がることになるが間違いありませんか?」と質問しました。
法人は「そうです…。」と認めました。
このような事実が看護師たちにきちんと伝えらているか疑問です。尚、看護師の基本給上限を引き下げることに組合は反対です。
組合「評価者はちゃんと評価できるの?どうやって訓練するの?」→法人「コンサルにトレーニングしてもらいます…」→組合「??」
新制度では、評価制度が取り入れられる予定でした。しかし、医療現場において評価というものは一般的ではなく、適切でもありません。
基本的に、営業職や小売業などの数字が伴う職場でなければ、評価制度導入は不可能と言っても過言ではありません。
また、医療現場において、明確な評価基準をどのように定めるかという高いハードルがありますし、評価者に対しての訓練も困難です。
組合は、評価の偏りが起こった場合、どのように是正していくか尋ねると、法人は「今回コンサルティングをやって下さっている業者さんに、評価が出来るように、数多くトレーニングしてもらう」と発言しました。
新人事制度で評価は、昇給や昇進・昇格、ボーナスに大きく関わることです。これほど重要かつ困難なことをコンサルティング会社に任せて良いはずはありません。
さらに繰り返しになりますが、医療従事者を評価することは一般的ではありません。
もっと言ってしまえば、実際の医療現場を熟知していないコンサルティング会社が主導して作った評価制度に評価されること自体、医療現場を軽視しているように思えます。
これらの法人の対応は、現場で働く職員たちを大切にしているとは言い難いです。
良い医療サービスを提供する為には、まず第一に職員たちの安定した生活が絶対条件です。そして、職員を大切にすることは、患者を大切にすることに直結します。
このことに鑑みても、新人事制度は恵佑会病院に適していません。新人事制度導入は撤回すべきと考えます。
不当労働行為発生??

団体交渉の終盤で、法人の発言がきっかけで不当労働行為救済申立をすることになります。
団体交渉の冒頭で、組合は法人に対し、新人事制度について、今後も誠実に協議をしてほしいと要請しました。
法人は、そのことに応じると答え、合意に至りました。
それにもかかわらず、そのことを書面化する段階になって、法人は堂々と書面化を拒否しました。
団体交渉での合意事項(確認事項)について、組合が書面化し、使用者側に調印を求めた場合、これを拒むと不当労働行為になります。
団体交渉はあくまで手段であり、目的は交渉で合意したことを書面化(労働協約化)することにあります。これは、労働組合法第1条で規定されています。
労働組合法第1条
この法律は、労働者が使用者との交渉において、対等の立場に立つことを促進することにより、労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について、交渉するために自ら代表者を選出すること、その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること、並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
しかしながら、団体交渉の場で法人は「文書化に応じる義務はない、調印はしない」と言い放ちました。
組合は、互いに誠意をもって、平和的に話し合いをすることを望んでいます。
組合として、紛争に発展することは非常に不本意ですが、このような違法行為を見過ごすことはできません。
8月19日、組合は、北海道労働委員会に不当労働行為救済申立を行いました。約1カ月後に調査が始まります。
法人には、これ以上大きな争いにならないよう、賢明な判断を望みます。
第1回団体交渉を終えて。感想など
最後に、1回目の団体交渉の感想など各組合員の声をまとめました。
- 院内で新人事制度の全容を把握できている人間はいるのか?誰なのか?
- 人事考査の評価の公平性が保てるとは到底思えない。
- また、人事考査という業務が増えることによる役職者の負担増について考えられていない。
- 若年層の救済と言いながら、コメディカルの若年層の賃金は下がる。若年層がほとんどいない役職者の基本給、職務手当どちらも上がることに疑問を感じる。
- 説明不足で賃下げになるのか、賃上げになるのかいまだに不明。よくわからない。
- 評価制度の内容が当院には適していないと思う。
- 若手層の給料の引き上げが目的だとの法人側の主張だが、若手層の基本給の増加率は、少なくとも、診療技術部職員の場合は、現制度よりも悪くなる。
- 賃金が下がる人の意見を聞こうとせずに、下げること自体が問題だと思う。
- 業者に任せっきりで、出来上がった案を精査することなく、全員の給料が増えると本当に思っていた法人の姿勢(思慮の欠如)が問題だと思う。きちんと話し合いたい。
- 団体交渉における、弁護士の存在意義が理解できない。
以上、組合員の声でした。尚、次回の団体交渉は9月4日(金)18時から開催します。ご支援をお願いします。