
9月4日18時から、第2回団体交渉を行いました。第1回目の団体交渉の報告記事はこちら
タイトルの通り、法人がまた不当労働行為を行いました。前回、不当労働行為を申し立ててから、舌の根の乾かぬ内に2回目の不当労働行為をやらかす…非常に残念でなりません。
組合としては、新人事制度について議論したいだけなのに、法人は一向にまともな交渉をする姿勢を見せません。
また、法人には法律のプロである弁護士が4名も就いているにも関わらず、なぜこのような事態になってしまうのでしょうか。
組合としては、本当に…本当に不本意ですが、不当労働行為救済の追加申立を行わざるを得ません。
…ということで、第2回団体交渉の報告です。
- 法人が文字がつぶれて読めない資料を組合に提出
- 不安は的中…法人がしどろもどろに?!第2回団体交渉開催
- 前回→法人「薬剤師手当は基本給に組み込むことになってます!」今回→法人「あ…やっぱ廃止でした…」
- 数値も計算もボロボロ…間違いだらけの資料
- 組合「年収が下がるベテラン看護師は何人くらいいますか?把握してますか?」→法人「把握していません」
- 法人「コメディカルの賃金が世間相場と比べて高いから下げます!」→組合「事務部長の賃金は世間相場と比べてどうなの?」→法人「調べてません…」
- 組合「今まで評価制度が無くて、業務に支障をきたしたことありますか?」→法人「それはありません!(キッパリ)」→組合「え、じゃ…いらないんじゃない?」→法人「…。」
- 法人「評価制度でモチベーションアップ!」→組合「その根拠は?実際、現場からそのような声が上がっているのですか?」→法人「いえ、実際には来ていません…」→組合「あっ…(察し)」
- 法人「上司と部下の賃金が逆転しているケースがあります!」→組合「根拠を示してください」→法人「残業代が原因でした…」→組合「え???」
- 組合「そもそも、残業は法人の命令でやっているんですが…?」→法人「…。」
- 組合「ところで、資料の説明をお願いします」→法人「できません!!」→組合「あっ…。(また不当労働行為やらかしちゃったよ)」
- 弁護士が4名もいて、なんでこんなことに…
- 不当労働行為救済追加申立へ
- あからさまなコンプライアンス違反…不適切な労働者代表選出
法人が文字がつぶれて読めない資料を組合に提出
第1回目の団体交渉で組合は、新人事制度についての不明な点の説明を求めました。しかしながら、こちらが納得できる回答はほとんどありませんでした。
また、法人は、前回の団体交渉で、新人事制度導入のいくつかある目的として「低賃金層の処遇改善」および「上司より部下の賃金が高いとされるケースの是正」を強調したため、組合は、その2点の根拠となる資料の提出を要求しました。
法人を疑っているわけではありませんが、1回目の団体交渉での法人の説明は、あまりにも矛盾が多く、とても納得できるものではありませんでした。
なので、組合としては、きちんとした根拠を示して説明して欲しいと法人に要請しました。
そして、要請から1ヵ月以上経った9月2日、法人側の弁護士から、(やっと)組合が要求した資料が郵送で届きました。
しかし、残念ながら、届いた資料の文字がとても小さいうえに、つぶれていて全く読み取れませんでした(もう!ずっと待ってたのに!)。すぐに弁護士に連絡をして、きちんと読み取れるものを再度送って欲しいと要請しました。
その日のうちにメールで資料は送られてきましたが、そのデータも「ちょっとマシかな…?」程度で、不鮮明なのは変わらず、非常に読みにくいものでした(普通の職場でこのような書類を出したら、上司や先輩からヤキ入れられるレベルのものでした…)。
団体交渉が始まる前から、法人の対応がこんな調子だったので、先行きがとても不安になりました。
不安は的中…法人がしどろもどろに?!第2回団体交渉開催

法人からは、代理人として弁護士が4名、札幌病院院長と事務部長2名が出席しました。組合からは、札幌地域労組本部員を含め20名が出席しました。
K事務部長は、前回の団体交渉で新人事制度について、組合からの質問に答えられず、しどろもどろになる場面があまりに多かったので、かなり緊張している面持ちでした。
前回→法人「薬剤師手当は基本給に組み込むことになってます!」今回→法人「あ…やっぱ廃止でした…」
前回の団体交渉で、法人は新人事制度で薬剤師手当が廃止されることについて、その分を基本給に組み込む主旨のことを発言していました。
しかしながら、法人は、今回の団体交渉では、廃止になると発言しました。
このことで、いかに法人が新人事制度について理解していないかが明らかになりました。
組合としては、あくまで新人事制度導入に反対であり、現在導入をストップさせている立場なので、法人のこの発言により、直ちに実害が生じることはありませんが、法人のいい加減さにとても疲れます。
数値も計算もボロボロ…間違いだらけの資料
今回の団体交渉に際して、組合は「新人事制度が導入された場合の組合員の賃金シミュレーション」の提出を要求していました。
法人は、1ヵ月以上の時間をかけて、組合員3名の賃金シミュレーションを組合に提出しました。
しかしながら、またもや残念なことに、その賃金シミュレーションの計算は間違いだらけでした。
詳しいことは割愛しますが、とてもじゃないですが、正式な話し合いに使えるものではありません。
法人は、「時間が無い中で作ったので、誤りがあった」と弁解しましたが、時間は1ヵ月以上もあり、要求したのはわずか3名分のシミュレーションです。(それなりに組合も忙しい法人に対し、気をつかっているんです!)
尚、資料は事務部長2名とコンサルティング会社が作ったとのことでした。職員を評価する前に、厳しく評価されるべき人間が他にいるのではないでしょうか。
組合「年収が下がるベテラン看護師は何人くらいいますか?把握してますか?」→法人「把握していません」

新人事制度では、役職の無い看護師の基本給の上限が7万円下がります。特に勤務年数が長いベテラン看護師に対する不利益は想像を絶します。
基本給が下がると退職金も下がります。このことは、前回の団体交渉で法人も認めています。組合は、これを非常に問題視しています。
そこで法人に対し「大きな不利益を被るベテラン看護師がどれくらいいるか、把握していますか?」と質問をしました。
このような看護師が存在することは、組合が前回の団体交渉で厳しく指摘しています。
しかし、法人はいとも簡単に「把握していません」と言い切りました。
法人の発言に対し、組合はさすがに怒りました。
長年、恵佑会病院を支えてきたベテラン看護師の賃金を下げ、退職金も大幅に下げることを全く気に留めていない態度は絶対に許せません。
組合の立場で、このようなことを言う事はなかなかありませんが、どうか法人にはしっかりして欲しいです。
我々は、法人を叩いてマウントを取ろうだとか、ストレスを発散させようなどと考えているわけではありません。
これから長く働くため、気持ちよく仕事をするため、より良い医療を提供するための議論を真摯に行いたいだけです。
その為には、法人にしっかりしてもらわないと建設的な話し合いが成立しません。
繰り返しになりますが、700名からの職員を抱える法人なんです。しっかりとした対応を望みます。法人が職員に対し、しっかりとした対応をするためなら、組合は協力を惜しみません。
法人「コメディカルの賃金が世間相場と比べて高いから下げます!」→組合「事務部長の賃金は世間相場と比べてどうなの?」→法人「調べてません…」
法人から提出された資料によると、ほとんどの『中堅コメディカル職員』の年収が下がることがわかりました。
そのことについて法人に理由を求めると、「世間相場と比べて、コメディカルの賃金水準が高い」「全道の医療職場と比べて高い」からと回答しました。
しかしながら、そもそも論として、道内には様々な規模の病院があります。技術力もピンからキリまであります。簡単に比較できません。
尚且つ、法人が主張している「世間相場」「全道の医療職場」の賃金水準は、コンサルティング会社が持ってきた数値を何の確認をせずに鵜呑みにして主張しています。
その上、道内でもトップレベルのがん専門病院である、恵佑会が平均値に合わせなくてはならない合理的理由はありません。全く説得力のない主張です。
もっと言ってしまえば、恵佑会の賃金は特別に高いものではありません。これは、働いている職員の皆さんが一番よくわかっていることだと思います。
また、組合が「新制度で、事務部長の賃金は、コメディカルと同じように道内平均になっているんですか?調べたんですか?」と質問すると、法人は小さな声で「いいえ…調べていません…」と回答しました。
さらに、組合が「それでは、なぜコメディカルだけが平均値に合わせなくてはならないのか?」「なぜコメディカルは平均で、事務部長は平均ではないのか?その理由はなにか?」と説明を求めると、法人は、理由を答えられずに「業者(コンサルティング会社)に頼んだ水準で出している」と回答しました。
法人の回答により、団体交渉の会場は、非常におかしな空気に包まれました。
当然です。話を整理すると、コメディカルの賃金を下げるのは、コンサルティング会社にそう言われたから。それ以外の理由はない。
コンサルティング会社を連れてきた事務部長の賃金は道内平均賃金もクソも関係なく上げていく。
これで納得するコメディカル職員はいません。いえ、全職員が納得出来ないのではないでしょうか。
組合「今まで評価制度が無くて、業務に支障をきたしたことありますか?」→法人「それはありません!(キッパリ)」→組合「え、じゃ…いらないんじゃない?」→法人「…。」

法人は、新人事制度の柱として『評価制度』の導入をしようとしています。
これは、前回の記事でも書きましたが、医療現場において評価制度は一般的ではなく、また、医療従事者の仕事を画一的に評価することは、ほぼ無理と言っても過言ではありません。
それにもかかわらず、法人は評価制度を導入しようとしています。
そこで組合は、団体交渉で法人に対し、「今まで評価制度が無くて、業務に支障をきたしたことはあるんですか?」と質問をしました。
法人は、きっぱりと「それはありません」と強調しました。組合は、「それでは評価制度を導入する必要はないのでは?」と法人に投げかけましたが、法人は目を丸くするだけで、なにも答えませんでした。
さらに組合は、「評価制度を導入することによって、現在の昇給額を維持するためには、卓越した優秀な成果実績を求めるA評価以上を獲得しなければなりません。入職したばかりの職員が、いきなりA評価を取ることは現実的ではない。評価制度は、入職したばかりの低賃金層職員の昇給を阻害するもので、法人が目的としている低賃金者の処遇改善とは矛盾している」と指摘しました。
法人は、組合の指摘に対し、何ら有効な回答を示しませんでした。
法人「評価制度でモチベーションアップ!」→組合「その根拠は?実際、現場からそのような声が上がっているのですか?」→法人「いえ、実際には来ていません…」→組合「あっ…(察し)」
法人側代理人のY弁護士は、「評価制度で職員のモチベーションが上がるのは一般的である」と主張しました。
その発言を受け、組合は「逆にモチベーションが下がります」「我々が日常的にどんな仕事をしているか分からない人に評価されたくないです」「医療提供者を評価するのは、評価者ではなく、あくまで患者である」と、現場を知る者ならではの意見を述べました。
また、Y弁護士の「同じ職種の先輩や上司からの評価は必要ではないか?」との発言に対し、組合は「一次評価は現場の上司だが、二次評価は、現場を何も知らない事務部長などが行い、その上、相対評価である」と反論し、現実的に同じ職場の上司からの評価が機能しないことを示しました。
新人事制度の評価システムは、一次評価は絶対評価ですが、二次評価は相対評価です。
一次で現場を知る上司によって正当に評価されたとしても、二次評価では、法人の予算に合わせて振り分けられます。すなわち、評価うんぬんよりも、予算に左右されるということです。
そもそも、売上のなどの数値が伴わない医療職場において、評価制度導入=モチベーションアップの根拠が不明です。
組合は、法人に「評価制度を導入してモチベーションが上がる理由を教えてください。そのような声が現場からあったのか?」と説明を求めました。
法人は、口ごもりながら「実際に来ているわけではない」と答えました。
必ずしも現場の声に従って病院経営をしなくてはならないという事はありません。しかしながら、客観的に見て、評価制度を直ちに導入しなくてはならない必要性は全くありません。
法人「上司と部下の賃金が逆転しているケースがあります!」→組合「根拠を示してください」→法人「残業代が原因でした…」→組合「え???」

前回の団体交渉で、法人は新人事制度導入の理由の一つとして、現行の年功序列制度の弊害として、上司と部下(一般職と役職者)の賃金が逆転しているケースがあると主張しました。
簡単に説明すると、役職者(年下)の賃金 < 一般職(年上)の賃金という構図になっているとのこと。
その問題を解消するために、新人事制度を導入するということなので、組合はその根拠となる資料の提出を法人に要求しました。
しかし、その資料に記載されていた逆転現象の理由に組合は言葉を失いました。
時間外手当の影響が大きく、一般職と役職者で賃金逆転が発生している
つまり、法人がさんざん主張してきた「賃金の逆転現象」は、残業代が原因で起こっているというです。逆に言えば、残業がなければ、全く問題ないということになります。
組合は法人に「今の状況を解消させたいのであれば、新しい賃金制度を導入するのでなく、残業を減らせばよいのでは?」「正当に働いた分を貰うのはダメなことなのか?残業で逆転しているのはしかたないのでは?」と質問をしましたが、ちゃんとした回答は得られませんでした。
さらに、「このように言われてしまうと、残業をしている一般職より、残業をしていない役職者のほうが給料が高くないとダメだと言われているように感じる」と法人に投げかけました。
法人は、力なく「そうではない…」と答えましたが、組合が「では、どういうことですか?」と聞き返すと、黙ってしまいました。
組合「そもそも、残業は法人の命令でやっているんですが…?」→法人「…。」
組合は、残業が前提となっている勤務体制に問題があることを指摘しました。
その上で、法人の命令で残業をしているのに、その結果、新人事制度によって、基本給が下げられるのは明らかにおかしいと主張しました。
しかし、法人からは具体的な反論はありません…いえ、反論できませんでしたと言ったほうが正しい表現かもしれません。
また、法人から詳しい説明がないので、断定はできませんが、提出された資料を見る限り、役職者の賃金には、役職手当が含まれていないことが読み取れます。
すなわち、単に基本給だけを取って、残業を含めた金額での比較をしたようです。普通に考えて、法人が比較対象とした数値が不適切なのは明らかです。
組合が法人に「これらの資料が適切な資料だと思ったのですか?」と尋ねると、法人は「安易に考えて出してしまった…」と力なく答えました。
さらに組合は、経験年数の違う職員を比較することは、間違っていると指摘しました。
今、この瞬間だけを切り取って比較すること自体が間違いの始まりで、例えば、現在30代の役職者と50代の一般職の賃金が逆転していても、30代役職者が50代になったとき、確実に今の50代一般職よりも多く賃金が貰える。
現行制度においては、生涯年収で考えても、法人が主張するほどの不利益は発生しないと考えます。
この組合からの指摘について、法人は「これから調べます…」と回答しました。
その場にいた組合員たちは、法人が発言した「これから調べる」の意味が分かりませんでした。7月に導入しようとしていた制度について指摘しているにも関わらず、「これから調べる」はあり得ません。
法人は、新人事制度導入について、今までいったい何をやっていたのでしょうか。こんな状況なのに7月から新人事制度を導入しようとしていたとは…背筋が凍ります。
そして、こんな調子なのに、今後も新人事制度を導入しようとしている法人のブレない姿勢は、ある意味すごいです。
組合「ところで、資料の説明をお願いします」→法人「できません!!」→組合「あっ…。(また不当労働行為やらかしちゃったよ)」
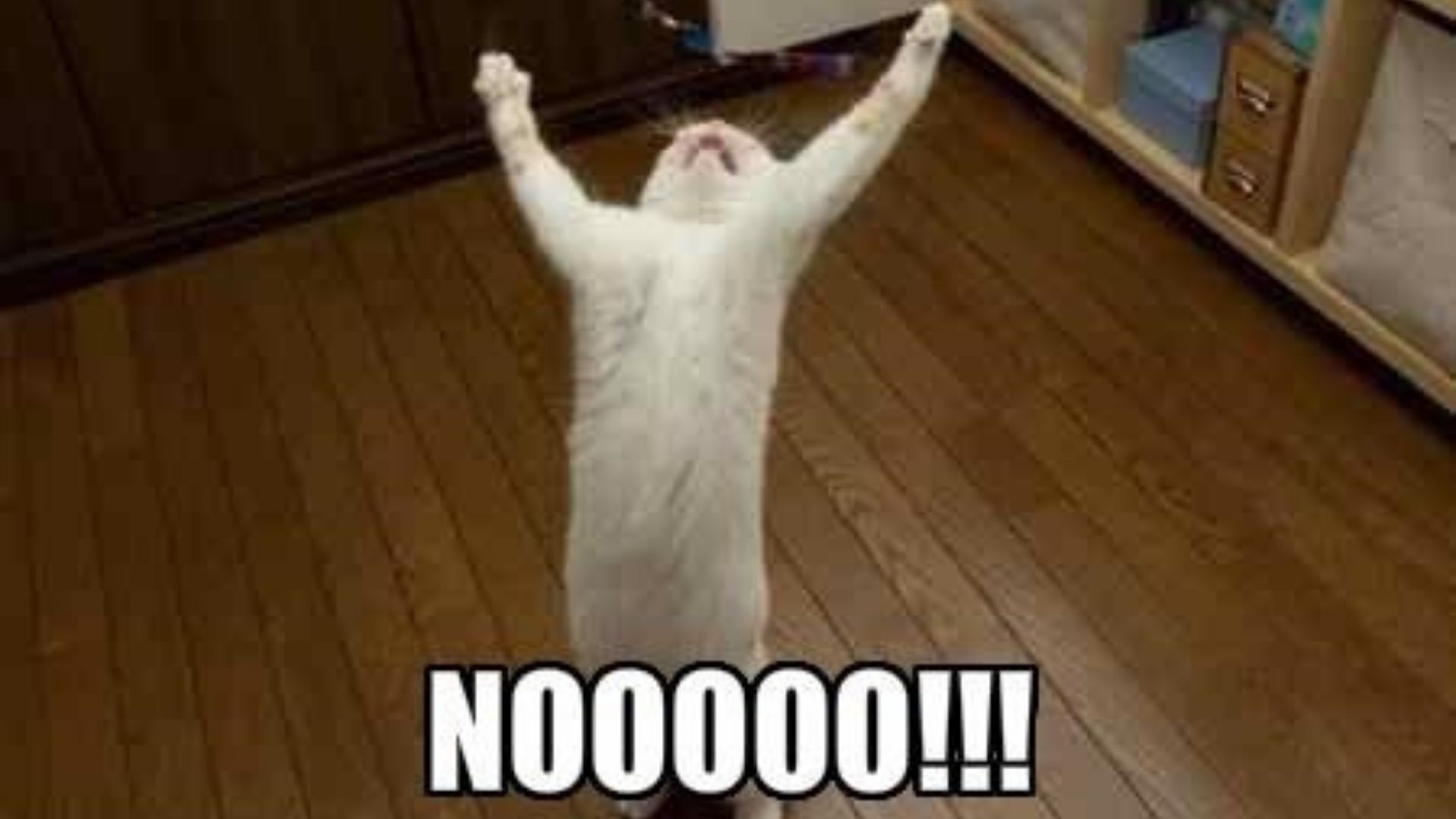
法人が提出した「賃金の逆転現象」を示す資料が、あまりにも分かりにくかったので、K事務部長に説明を求めました。
組合がK事務部長に「資料を我々にわかるように説明してください」と質問をすると、K事務部長は下を見たまま動かなくなってしまいました。
K事務部長が急に具合が悪くなってしまったのかと思い、組合は心配になって「K事務部長…?」と呼びかけると、元気なお返事があったので、具合が悪いわけではないようでした(よかった!)。
そして、改めて、組合が法人に説明を求めた時、不当労働行為事件は起きました。
組合「K事務部長、資料の説明をお願いします。」
K事務部長「…。」
組合「説明できますか?(ん?)」
K事務部長「…。」
組合「資料の説明できるんですか? できないんですか?(あれ…?)」
K事務部長「できませんッ…!!」
組合「あーあ…。」
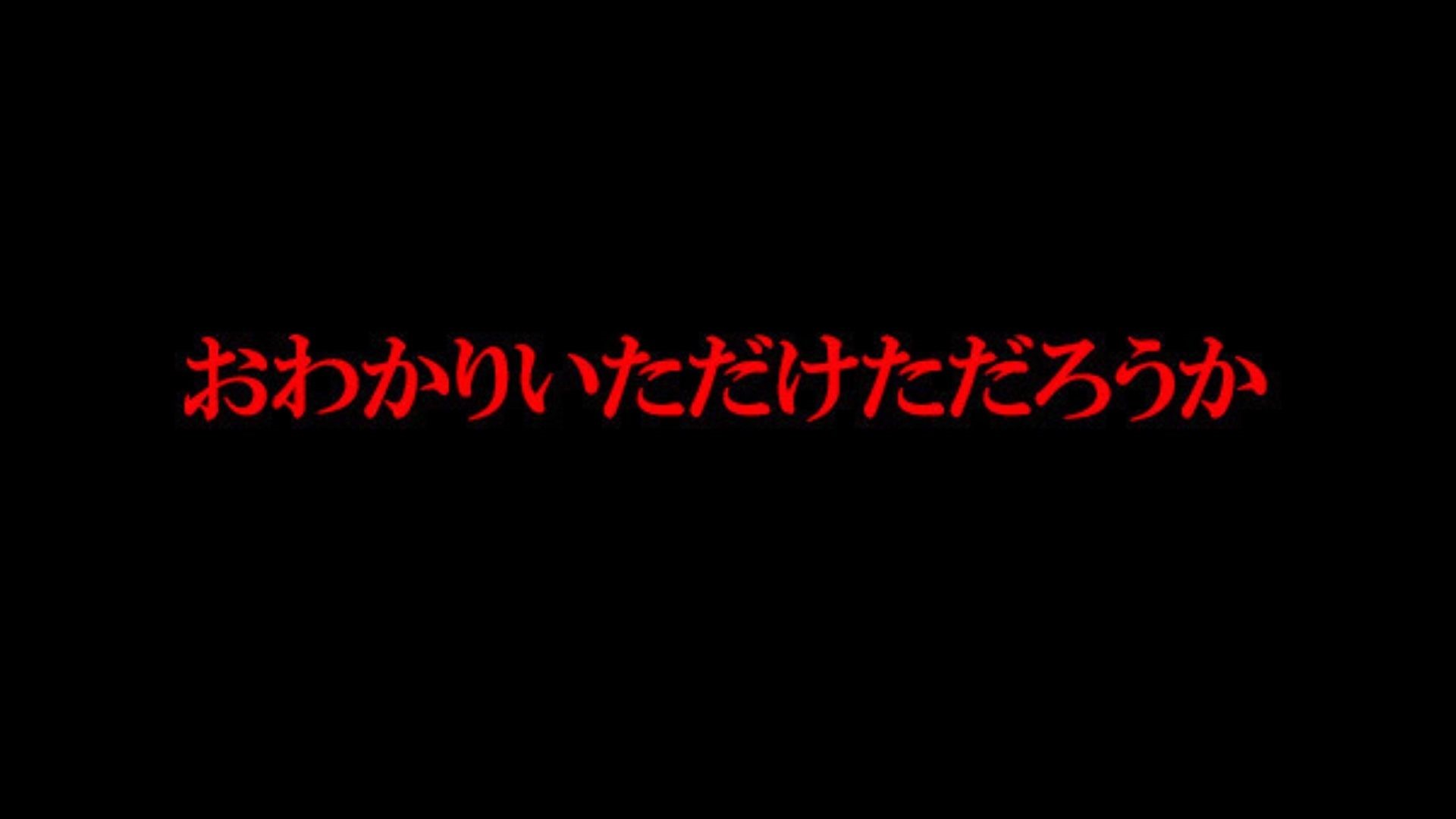
もちろん、他の法人側出席者も資料の説明はしませんでした。完全にやらかしています。
団体交渉で、使用者には誠実交渉義務が課せられます。誠実交渉義務の解釈は非常に広いです。
その中でも、使用者は組合に対し、交渉議題について口頭だけの説明ではダメで、具体的な資料を提出して、妥結に導くように誠意をもって交渉しなくてはいけません。
今回のように、口頭での説明もろくにせずに、その上、堂々と資料の説明をしない(法人が自分で用意した資料なのに!)ことは、不当労働行為です。ましてや、賃下げに関わる重要な資料です。説明責任はより一層重たくなります。
組合としては、非常に残念ですが、不当労働行為があった以上、労働委員会に不当労働行為救済申立をしなければなりません。
誠実交渉義務とは
使用者は、自己の主張を相手方に理解し、納得することを目指して、誠意をもって団体交渉に当たらなければならず、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなどし、また、結局において、労働組合の要求に対し、譲歩することができないとしても、その論拠を示して反論するなどの努力をすべき義務があるのであって、合意を求める労働組合の努力に対しては、右のような誠実な対応をつうじて、合意達成の可能性を模索する義務がある。
カールツアイス事件・東京地判(平成元.9.22判時1327号145頁、シムラ事件・東京地判平成9.3.27労判720号85頁も同旨)
弁護士が4名もいて、なんでこんなことに…
目の前で堂々と不当労働行為を行ってしまったK事務部長に対し、法人側弁護士は一切フォローをしませんでした。
本来であれば、このようなことが起きないように、法律のプロフェッショナルである弁護士がいると思うのですが。(あと、計算間違いや数値の違い、資料の内容とかもチェックしていなかったのかしら…?)
K事務部長は、不当労働行為について何の知識も持っていません。もっと言ってしまえば、K事務部長に限らず、ほとんどの事業主が不当労働行為についての知識を持っていません。
そこをカバーするために弁護士がいるのではないでしょうか。無用な法律違反行為が起こらないように弁護士がサポートすることが本来の役目だと思います。しかも、今回は4名も弁護士がいました。
それにも関わらず、弁護士全員がK事務部長の不当労働行為について、無反応でした。
ちなみに、団体交渉の終わり際に、札幌病院の院長が、不当労働行為に抵触しそうな発言をうっかりしてしまったときは、しっかりと瞬時に光の速さで弁護士がフォローしていました。
なぜ院長のことはフォローするのに、K事務部長のことはフォローしないのでしょうか。K事務部長のことはどうでも良いのでしょうか。
K事務部長!もし法人に切り捨てられるようなことがあれば、組合に連絡をください。組合はあなたのことも守ります。
それにしても、これまでに2回団体交渉を行いましたが、弁護士が4名も団体交渉に出てくる意味がわかりません。
団体交渉中、ほとんどしゃべりませんし、K事務部長が不当労働行為をやらかしている場面を完全無欠のスルーでした。
組合員からも、「弁護士が何のために来ているのかよくわからない」との声が多数寄せられています。
あ、でも、そういえば良いこともありました!弁護士が4名もいるので、団体交渉が終わったあとに、会場のテーブルやイスを手早くお片付けができます。いつも本当に助かっています。その点は、ありがたく思っています!これからも宜しくお願い致します!
不当労働行為救済追加申立へ
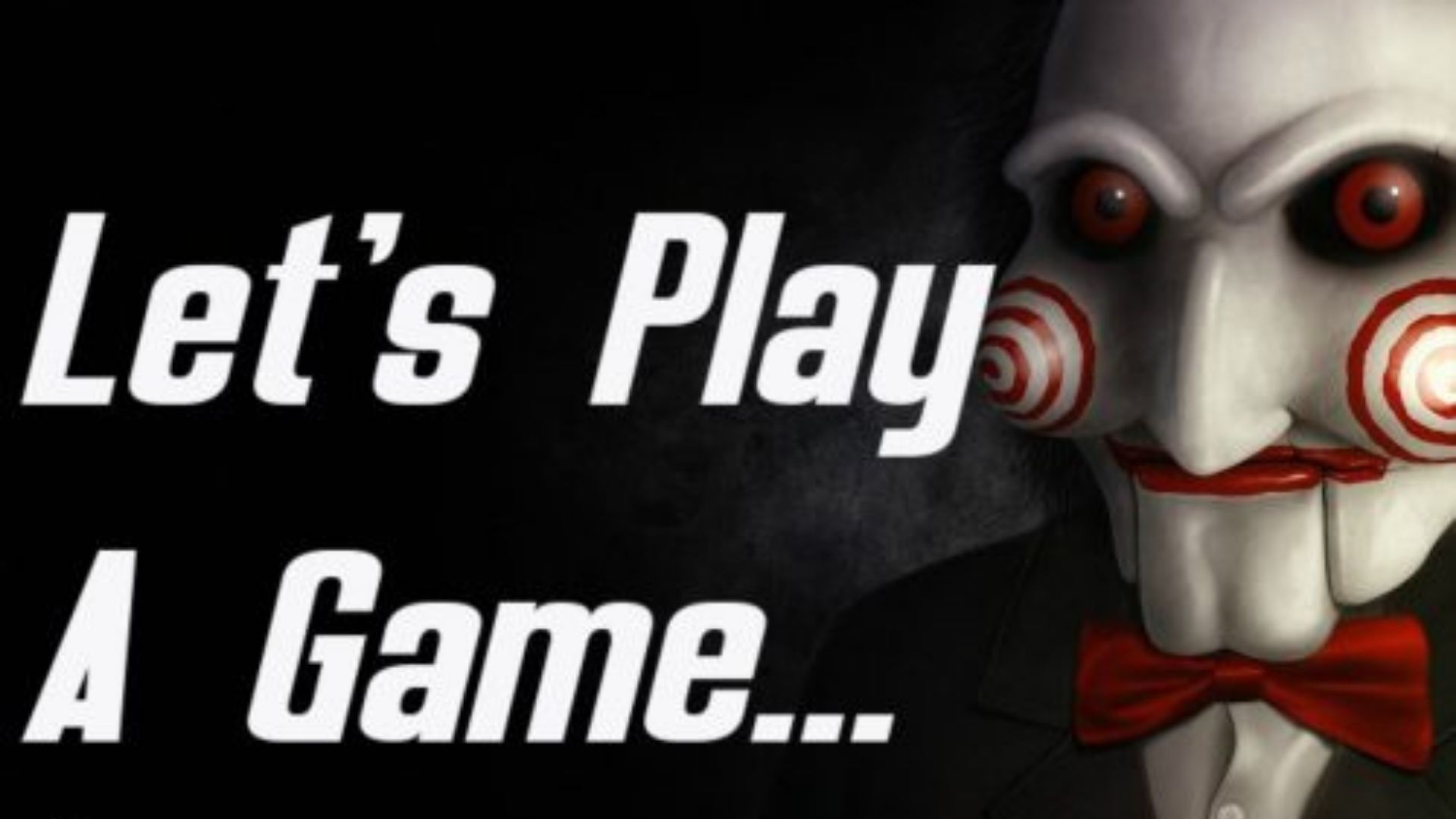
9月15日、組合は、北海道労働委員会に不当労働行為救済追加申立書を提出してきました。
本当に不本意です。なぜこのような事態になるのでしょうか。同じ病院の組合でも大野記念病院支部は、労使共に円満です。いえ、超円満です。
もちろん大野記念病院にも代理人弁護士が就いています。団体交渉においても弁護士が参加します。しかしながら、このように短期間で2回も不当労働行為救済申立をするような事態になっていません。(まぁ、当然ですが。)
むしろ、労使間の問題解決に積極的に取り組んで、実際に労使円満を実現しています。弁護士のおかげで法人も組合も本当に助かっています。
恵佑会病院では、おそらく今後も不当労働行為が、かなりの高確率で起こるかと思います。不当労働行為があれば、組合はその都度救済申立をしなければなりません。
このような不毛な争いは、どうすればなくなるのでしょうか?
法人には、目を凝らして、問題がどこにあるのかを見極めて欲しいです。
ちなみに大野記念病院を担当しているのは、「橋本・大川合同法律事務所」という弁護士事務所です。非常に高い問題解決能力を持っています。気になる方は、検索してみてください。
あからさまなコンプライアンス違反…不適切な労働者代表選出

これまで法人は、不適切な方法で「労働者代表」を選出してきました。そして、不適切な36協定書を作成し、労働基準監督署に提出していました。
36協定とは
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」といいます。法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づき、労働者代表、あるいは過半数労働組合との労使協定(36協定)の締結と所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
※ちなみに労働者代表の選出方法については、最近めちゃくちゃ厳しくなっています。
このことは、組合が厳しく指摘し、法人は団体交渉で不適切であることを認めました。
その上で、早急に改善すると発言していますが、そもそも恵佑会ほどの大きな病院で、今までこのようなずさんな労務管理をしていたこと自体あり得ません。
しかも、事務部長が二人もいて、なぜこのような基本的なことが出来ていなかったのか。
もし評価制度が取り入れられたら、真っ先にじm
法人は、組合の指摘を受けて、9月15日付の院内文書で労働者代表選出を適切な方法で選出するとしていますが、これまでさんざんいい加減にやってきた法人が、いきなり改善できるとは思えません。
職場には守るべき真っ当なルールがあります。労働者代表の民主的な選出は、最も基本的なルールです。そのことを法人が軽んじないように組合が抑止力となって、職員が安心して働ける職場づくりを進めていきます。
次回団体交渉の日程は、近日お知らせできると思います。また、労働委員会の進捗についても随時ウェブ記事にて発信していきます。それでは、引き続き支援をお願いします。
恵佑会ユニオンのTwitterアカウントはこちら
最新情報を発信します!フォローお願いします!