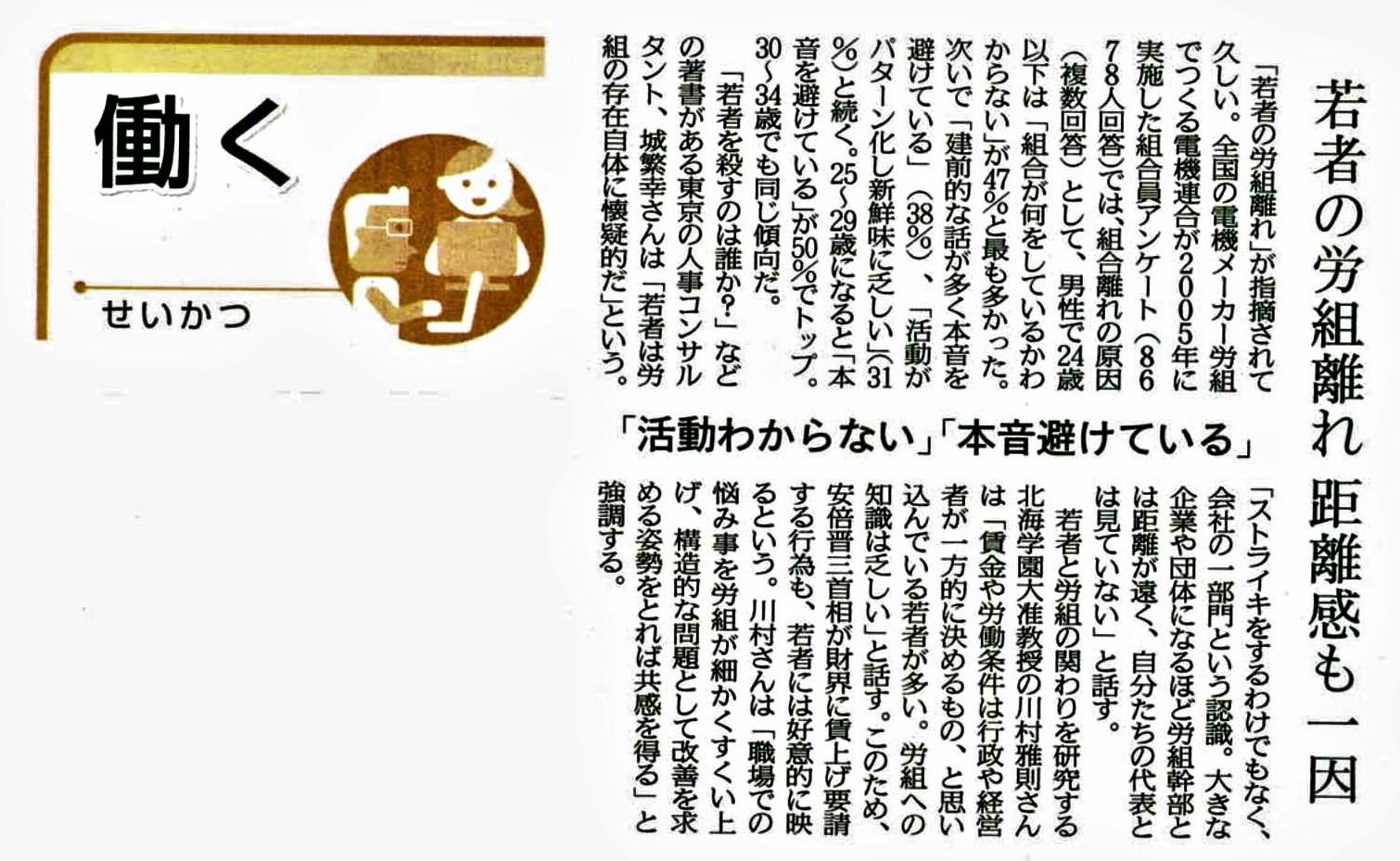札幌の老舗車体メーカーで、以前は組合活動や労働問題に関心のなかった若者たちが労働組合を結成して1年余りが過ぎた。
この間、残業代支払いを求めて団体交渉を始め、24時間ストも決行した。いま会社側とは法廷闘争が続いている。 (磯田佳孝)
札幌の車体メーカーの若手社員ら 労組結成1年
札幌市東区にある消防車両車体製造の田井自動車工業。作業着に赤い腕章をつけて働くのは、札幌地域労組田井自動車支部長の橋本良太さん(34)だ。
「仕事中も出張先でも腕章は外しません。今も闘争中ですから」。日焼けした顔に笑みが浮かぶ。
同社は創業1924年(大正13年)の老舗企業で従業員50人(昨年末現在)。道内の消防署に配備される消防車両の製作・整備を行う。だが、納期近くには深夜作業も続くうえ「給料が安い」「残業が多い」と不満がたまっていた。
「よく分からないけど、労働組合があれば会社と交渉できるらしい」。20代の従業員がインターネットで検索して気付いた。うち1人が昨年3月、個人加盟もできる札幌地域労組を探し出して、相談した。
それまで、政党や労働団体とは無縁だったが、組合活動に抵抗感を感じる余裕すらなく行動を続けた。水面下で直接1人ずつ声をかけ、労働組合に関する勉強会も開いた。
5月末に札幌地域労組の支部の形で労組を発足させ、20代、30代の24人が参加した。まず求めたのは残業代の支払いだ。
同社では毎月定額の「残業手当」があるが、労組は「残業実態を反映しておらず、事実上は基本給の一部」と主張する。
道労委決定 9月にも
団交は当初順調に進んだが、会社側が打ち切り。個々の労働紛争に対応する労働審判に移ることを組合員個人に通告したため、労組は「不当労働行為だ」と昨年8月に道労働委員会に救済申し立てをした。
翌月には抗議の24時間ストを決行。また、未払い残業や団交拒否をめぐる法廷闘争に入った。
この間、仲間5人が労組を去った。「もう、やめておけば」「会社がつぶれたらどうするの」。妻と2人の子どもがいる橋本さんに周囲からこんな声もかかる。
不当労働行為をめぐる道労委の決定は9月にも出るとみられる。「組合員はこの仕事を愛している。きっと会社が分かってくれる日がくる」と信じる。
消防士とも交流、刺激に
新たなつながりも生まれた。道内の消防職員でつくる北海道消防職員協議会との交流だ。
激励の後の懇親会で、現場の消防士と消防車両の仕様について熱っぽく語りあかした。「作り手として実際に消防士の人の生の声が聞けたのは初めて」。組合員も大きな刺激を受けた。
21日の参院選では、若者の労働問題は他の争点の中で埋没し、道選挙区の候補者が橋本さんたちを訪れることもなかった。
「でも、声を上げ続けないと」。橋本さんはあきらめない。
田井自動車側は取材に対し「対応は弁護士に任せている」としており、担当弁護士は「お話することはない」との回答だった。

若者の労組離れ 距離感も一因
「若者の労組離れ」が指摘されて久しい。
全国の電機メーカー労組でつくる電機連合が2005年に実施した組合員アンケート(8678人回答)では、組合離れの原因(複数回答)として、男性24歳以下は「組合が何をしているかわからない」が47%と最も多かった。
次いで「建前的な話が多く本音を避けている」(38%)、「活動がパターン化し新鮮味に乏しい」(31%)と続く。
25~29歳になると「本音を避けている」が50%でトップ。30~34歳でも同じ傾向だ。
「若者を殺すのは誰か」などの著書がある東京の人事コンサルタント、城繁幸さんは「若者は労組の存在自体に懐疑的だ」という。
「ストライキをするでもわけでもなく、会社の一部門という認識。大きな企業や団体になるほど労組幹部とは距離が遠く、自分達の代表とは見ていない」と話す。
若者と労組の関わりを研究する北海学園大准教授の川村雅則さんは「賃金や労働条件は行政や経営者が一方的に決めるもの、と思い込んでる若者が多い。労組への知識は乏しい」と話す。
このため、安倍晋三首相が財界に賃上げ要請する行為も、若者には好意的に映るという。
川村さんは「職場での悩み事を労組が細かくすくい上げ、構造的な問題として改善を求める姿勢をとれば共感を得る」と強調する。